良い?悪い?ピーマンの食べ合わせと嬉しい3つの栄養を徹底解説!
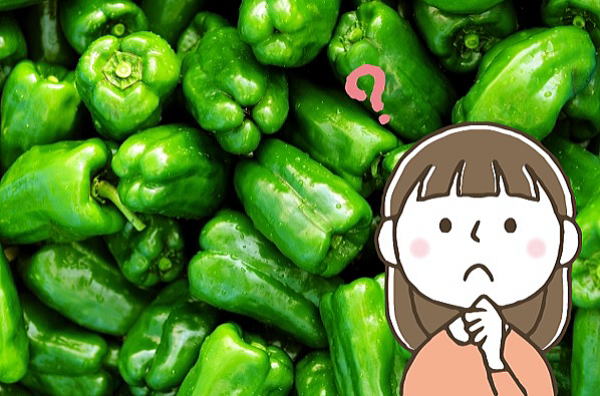
更新:





ピーマンには特有の青臭さと苦味があり、子供が嫌いな食べ物の代表とも言えます。ピーマンはβカロテン、ビタミンC、ビタミンE、カリウム、鉄分、食物繊維などを豊富に含んでいます。ピーマンのビタミンCは丈夫な組織に守られているため、加熱調理してもあまり壊れる心配がありません。ピーマンの食べ合わせについて、ぜひとも知っておきましょう。
目次
ピーマンはどんな食材?

ピーマンはトウガラシの仲間であり、主に緑色のものを食していますが、これは未熟な果実の状態で収穫しているからです。ピーマンも成熟すると赤や黄色になりますが、トウガラシのように辛み成分のカプサイシンは含んでいません。
ピーマンには独特な青臭い風味と苦みがあるため、子供が嫌いな野菜として名前が上がりやすいのですが、最近では苦みを抑えた品種も開発されています。
炒め物や揚げ物の具材として重宝されており、緑色が鮮やかであるため、料理に彩りを与える存在となっています。
ピーマンに含まれている栄養素

■ピーマンのビタミンCは壊れにくい
ピーマンはβカロテン、ビタミンC、ビタミンE、カリウム、鉄分、食物繊維などを含んでいます。特にビタミンCが多く、コラーゲンの生成に関わり肌にハリを与えたり、シミやそばかすを防ぎます。
ピーマンのビタミンCは丈夫な組織に守られているため、加熱調理してもあまり壊れる心配がありません。
■特有の匂いの原因はピラジン
ビタミンEは抗酸化力が強く、老化の原因となる活性酸素の働きを抑えるので「若返りのビタミン」と呼ばれています。ピーマンは青ピーマンよりも黄色や赤のほうがビタミンなど栄養が多く含まれており、ビタミンEだと赤ピーマンのほうが青に比べて8倍も多く含んでいます。
ピーマンの独特の匂いはピラジンという物質によるものです。このピラジンには血栓の生成を抑え、血液をサラサラにする効果があると言われています。
ピーマン100gあたりの栄養価

以下の表では、ピーマン100gあたりに含まれているエネルギー量や、主要なビタミン・ミネラルなどの含有量を示しています。単品からの栄養摂取に偏ることなく、さまざまな食材を上手に食べ合わせて、バランスよく栄養を摂取しましょう。
| エネルギー | 20 kcal |
| 炭水化物 | 4.64 g |
| 糖類 | 2.4 g |
| 食物繊維 | 1.7 g |
| 脂肪 | 0.17 g |
| ビタミンA相当量 | 18 μg |
| βカロテン | 208 μg |
| ビタミンB1 | 0.057 mg |
| ビタミンB2 | 0.028 mg |
| ビタミンB3 | 0.48 mg |
| ビタミンB5 | 0.099 mg |
| ビタミンB6 | 0.224 mg |
| 葉酸 | 10 μg |
| コリン | 5.5 mg |
| ビタミンC | 80.4 mg |
| ビタミンE | 0.37 mg |
| ビタミンK | 7.4 μg |
| カリウム | 175 mg |
| カルシウム | 10 mg |
| マグネシウム | 10 mg |
| リン | 20 mg |
| 鉄分 | 0.34 mg |
| 亜鉛 | 0.13 mg |
| マンガン | 0.122 mg |
栄養効果を高める食べ合わせのポイント

ピーマンは夏野菜の定番であり、ビタミンCやβカロテンなどの各種ビタミンを豊富に含んでいます。このピーマンとの食べ合わせでおすすめなのが豚肉です。豚肉には食材の中でもトップクラスのビタミンB1が含まれています。
ビタミンB1は糖質のエネルギー代謝に関わっており、不足すると疲労物質である乳酸がたまってしまいます。夏バテしやすい時期には、豚肉のビタミンB1を併せて摂ることで、体力増強や夏バテ防止効果が期待できます。
また、ピーマンに豊富に含まれているビタミンCは細胞組織で守られているため、加熱調理しても壊れにくいという特徴があります。
ビタミンCは「美肌のビタミン」とも呼ばれており、コラーゲンの生成や、シミの原因となるメラニン物質の産生を抑える働きがあると言われています。
このビタミンCの働きを助ける食べ合わせとして、βカロテンを豊富に含むニラや小松菜、ほうれん草が挙げられます。βカロテンは髪や爪、皮膚、粘膜を健康に保つ働きがあると言われており、ビタミンCの働きとともに美肌効果が期待できます。
一緒に食べるとよい食材
期待できる効果

| 一緒に食べるとよい食材 | 期待できる効果 |
|---|---|
| ニラ 小松菜 ほうれん草 鶏卵 |
ガン予防 老化防止 美肌効果 |
| カキ イカ やまいも 玄米 |
滋養強壮、 糖尿病予防 |
| もやし 牛肉 豚肉 |
夏バテ解消、 クーラー病の改善 |
| コンニャク タマネギ ふき |
高血圧、動脈硬化の予防 |
| 出典1:厚生労働省|日本人の食事摂取基準(2020年版)|脂溶性ビタミン 出典2:厚生労働省|日本人の食事摂取基準(2020年版)|水溶性ビタミン 出典3:厚生労働省|日本人の食事摂取基準(2020年版)|ミネラル(多量ミネラル) 出典4:厚生労働省|令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要 出典5:文部科学省|日本食品標準成分表2020年版(八訂)|青ピーマン/果実/生 |









































